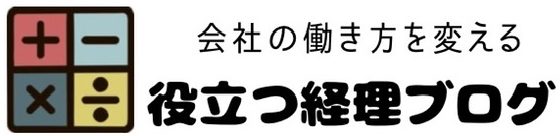この記事で解決できるお悩み
この記事を書いた人
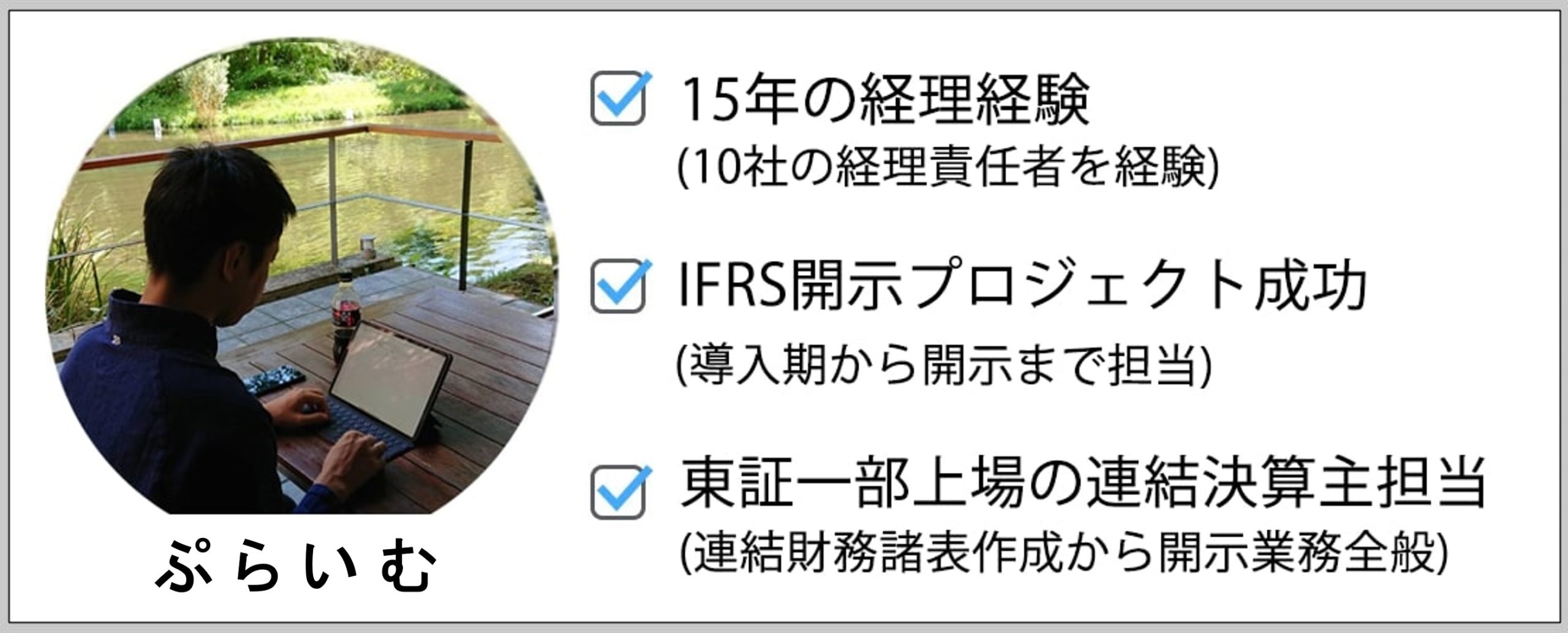
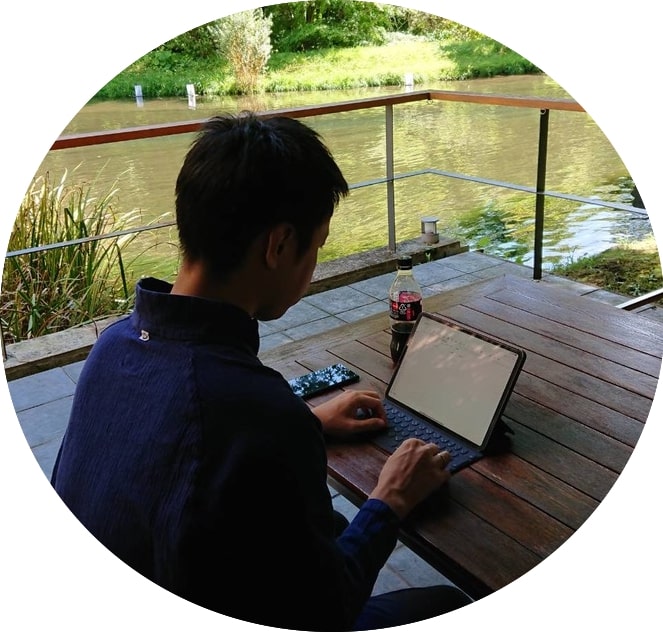
未知識から転職できたので経験談を解説しますね!
この記事ではIFRS適用企業に興味があるけど、未経験で不安に感じている人に向けて書いています。
近年は新規上場をIFRS基準で準備している会社があります。IFRS基準で開示している会社は単体決算はかなりの少数なので、ほとんどの企業が連結決算をしています。
後で解説しますが、米国基準で掲示している会社でIFRS基準の開示に変更している会社もあるんです。これからもIFRS基準の会社は増えていくと予想されていますよ!
この記事は次の4つの流れで解説をします。
step
1IFRS開示で必要な準備
step
2IFRS適用企業で学習する方法
step
3未経験でも大丈夫!
step
4IFRS適用企業で働く方法
※『IFRSの概要を知りたい!』という人は、以下記事で詳しく解説しているので読んで下さいね。
-

-
【IFRSとは?】IFRS導入企業で働くベテラン経理が基礎を解説【国際会計基準とは?】
続きを見る
それでは、順番に解説をしていきます!
IFRS開示で必要な準備
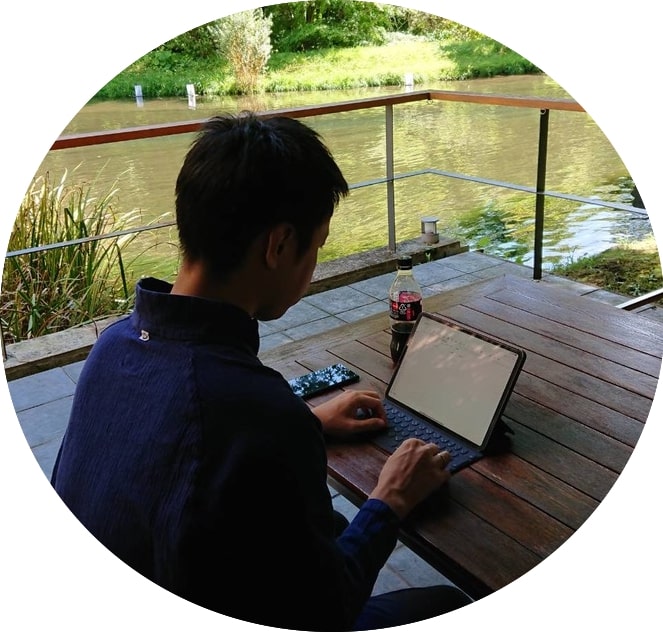
IFRS開示で必要な主な準備業務
- 日本基準とIFRS基準の差異の確認
- 注記の開示方法を検討
- 連結決算ソフトを使ってデータの移行作業
- IFRSに対応した連結パッケージの作成
この中でも『①日本基準とIFRS基準の差異の確認』が大変です。IFRS開示の多くは連結決算です。子会社の会計処理もIFRS基準に調整する必要があるので、説明や打合せを何度も重ねました。
※『IFRS基準と日本基準の差異を詳しく知りたい!』という方は、以下記事で読んで下さいね。
-

-
【初学者必見】IFRSと日本基準の違いをIFRS開示経験者がわかりやすく解説【JGAAP差異】
続きを見る
わたしはIFRSの知識はなく、それぞれの業務に関わりました。『注記の開示方法の検討』と『連結決算ソフトを使ってデータの移行作業』の準備をしました。
なぜIFRS未経験で転職できたか?
わたしが「IFRSの知識がないのに、IFRS開示の準備会社に採用できたんだろ?」と疑問に感じていました。
後で聞いた話では『IFRSの開示経験がある人はとても少なく、連結の知識があれば採用できる可能性が高い』からでした。
私はIFRSに関する知識がなかったので、最初は周りに迷惑をかけてないかとても心配で、必死で頑張りましたが失敗の連続でした
それでも諦めずにプレッシャーとストレスを感じながら前向きにIFRSに関する知識を身につけました。
続ける事で開示をする頃にはIFRSに関する知識だけでなく、どのように子会社から情報を収集するのが最適化を理解できたんです。
実務でどのように経験を積むのが良いかは『IFRS適用企業の学習方法は?』で解説します。
※『IFRSの学習方法を詳しく知りたい!』という方は、以下記事で読んで下さいね。
-

-
【連結決算】IFRS(国際財務報告基準)の学習方法をベテラン経理が解説【プロジェクト成功へ導く】
続きを見る
今がIFRSを経験をするチャンス
未経験でIFRS関連入企業に転職を考えている人は多いです。
しかし「未経験で転職できるかな?」「また勉強するのはしんどいな」と考えてしまい躊躇する人が多いです。
IFRSを経験することで間違いなく次の2つのメリットがあります。
①経理に関する知識が広がる
②市場価値があがり年収が増える
わたしは転職をする事で『前職を続けていると得られない知識』と『知識を得たことで市場価値が上がり年収が増加』しました。
長くても2年間頑張ることで、今後の経理として働くキャリアが大きく変化しますよ!
IFRS関連企業で学習する3つの方法
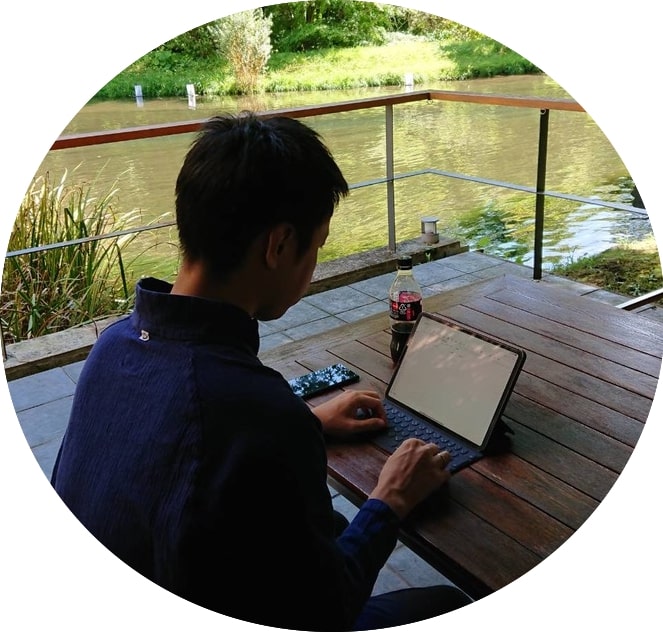
私はIFRS未経験でIFRS準備会社に転職しました。
わたしは転職をした当初は毎日が不安でいっぱいでした。
「他の人はIFRSについて理解しているんだろうな…」
「今から追いつけるかな…」
そんな不安の毎日だったので上司に現状を相談しました。すると上司自身も知らないことが多く不安を感じていました。
誰でも新しい事を始める時は不安を感じます。そんな時は手を動かして頭を働かせて学習をすれば必ず知識は身につきます。
わたしが実務経験の中で知識をつけるために、3つの方法を試しました。
実務経験から知識を身に着ける3つの方法
わたしは3つの方法でIFRS開示に必要な知識を身につけました。非常にシンプルな行動です。シンプルな行動ですが、転職した後も成果を出す事が出来ますよ!それぞれ解説をしますね。
監査法人に相談
IFRS基準で開示するためには、監査法人の監査承認が必要になります。なので、どのような状況でも監査法人に相談をしてIFRSの開示に向けて準備をします。
しかし『大手監査法人』と『大手以外の監査法人』ではIFRSに対する理解が異なるので注意が必要ですよ。
監査法人に相談するにあたって、『大手監査法人』と『大手以外の監査法人』の『メリット』と『デメリット』を解説しますね。
監査法人によるメリットデメリット
大手監査法人を使うメリット
大手監査法人を使うメリットは3つあります。
- IFRSに特化したチームが存在する
- 難しい論点は監査法人内で答えを出せる
- IFRS特有の論点を教えてくれる
監査法人で働く公認会計士の資格を持った人でも、全ての論点に詳しい人はほとんどいません。ましてやIFRSの論点になると顕著です。
大手監査法人のメリットは、規模が大きく監査法人内で各論点の専門家がいる事です。IFRSの論点で疑問点があれば、監査法人内で答えを出してくれます
IFRSの開示は論点が多いので、一つの論点に時間をかけるのは得策ではありません。なるべく疑問を残さずに、論点を解決するには大手監査法人はとても心強いです。
大手監査法人を使うデメリット
大手監査法人を使うデメリットはありませんでした。
大手監査法人の方が規模の小さい監査法人より報酬が高い傾向にありますが、担当者としては気にする項目ではありません。
大手監査法人に話す機会があると安心をして相談が出来ます。
大手以外の監査法人を使うメリット
大手以外の監査法人を使うメリットは3つあります。
ここでは、担当の監査法人がIFRSに関する知識がない前提です。大手以外はIFRSの知識がない監査法人がとても多いです。
- 原文を読むので読解力が身につく
- 監査法人に説明できるように理論武装する
- 他社事例にない注記方法を柔軟に作成できる
これはメリットよりも、結果として良い経験になるイメージです。自分自身で考える時間が多いので、問題点を見つけて解決をする力がつきます。
転職をすると、以前と同じ環境で質問が出来るとは限りません。自分自身で問題解決することは、どこの会社で働く場合でも強みになります。
大手以外の監査法人を使うデメリット
大手以外の監査法人を使うデメリットは3つあります。
- 業種特有の論点を逃してしまう可能性がある
- 誤った開示がされてしまう可能性がある
- 時間がかかる
大手以外の監査法人ではIFRSに関する知識が不足していることが多く、論点が固まった後に再度検証などの工数が発生することがありました。
最悪の場合は、検証を重ねた結果の解釈に誤りがあり、開示が適切でない場合です。この場合は影響が大きい場合を除き、開示書類を再提出しない可能性が高いです。
業務量については、多くの人は『通常業務』と『IFRSプロジェクト』を担当します。業務量が倍近くになるので、閑散期もやるべきことが山積みになります。
外部のコンテンツを活用する
知識をつけるために、外部のコンテンツを利用することができます。
わたしは知識習得や注記を完成させるために、外部セミナーやIFRS専門サイトやアウトソーシングを利用しました。それぞれのメリットとデメリットを解説しますね。
外部コンテンツのメリットとデメリット
外部セミナーに参加するメリット
外部セミナーに参加するメリットは2つあります。
- IFRSの全体像やトレンドが理解できる
- 質問の時間に自社の課題のアドバイスをもらえる
外部セミナーの主催は大手監査法人が多いです。常に最新の基準や動向を調べているので、自社に関連する内容を理解するのに良いです。
さらに、外部セミナーは申込者から主催者に質問ができる良い機会です。質問をした後に、他のセミナー参加者から同様の課題を抱えている場合は、声をかけられることがあります。
IFRSに関連する会社の人とつながりを持てる機会は『セミナー』や『親睦会』が主なので、会話をする事で思わぬ発見をする事があります。
外部セミナーに参加するデメリット
外部セミナーに参加するデメリットは1つあります。
- 質問に対する答えに責任がない
セミナーでは自社の状況を全て伝えることは難しいので、回答が自社の状況と合っていない場合があります。
セミナーで質問をして回答を得る事が出来ても、それを答えとする事は出来ません。自社の監査法人とセミナーで得た回答を相談をして、答えを出す必要があります。
外部セミナー以外を利用するメリット
外部セミナー以外を利用するメリットは3つあります。
- 研究部はIFRSの刊行物や統計資料がまとめられている
- 研究部はIFRS開示実績の他社事例がまとめられている
- アウトソーシングはIFRS専門の会計士に相談ができる
研究部の利用
研究部はIFRSに関する情報を集めた有料サービスです。研究部ではIFRSに関す様々な情報がまとめられています。
①開示書類の手引
②条文に紐づく他社事例
③任意開示の他社事例
わたしが特に利用していたのは、注記を作成する時に参考にする『条文に紐づく他社事例』です。気になる条文を選択すると該当する他社事例が確認できるんです。
IFRSの注記は日本基準に比べて、自由に作成が出来ます。ただ、自由に作成が出来る為に選択肢が多くて、どのように注記をするか困りました。
そんなときに役に立つのが『他社事例』です。研究部では条文に紐づいて他社の注記を検索できるので、注記を作る時にとても役立ちました。
アウトソーシングの利用
アウトソーシングの利用は、IFRSの論点が決まった後にとても役立ちました。
IFRSの有価証券報告書の注記の量は、日本基準に比べて「2倍~3倍の量」があります。この量を自社で作成するのは、とても工数が必要になります。
有価証券報告書の入力を全てをアウトソーシングするサービスがあります。このサービスを利用すれば、根拠資料を作成すれば『入力』と『タグ付け』をしてもらえます。
明らかな間違いや、他の注記との関連性を確認して不整合があれば指摘をしてくれます。料金は高額になりますが、勉強になるので大変良いサービスでした。
外部セミナー以外を利用するデメリット
外部セミナー以外を利用するデメリットは1つあります。
- 相談が出来ない
研究部は調べるにはとても役に立つツールですが、専任のサポーターはいません。なので、電話で質問をする事が出来ないんです。
研究部で調べた内容を監査法人に相談する必要があります。また、参考他社の数がとても多いので、要領を良く調べることが難しいです。
他社事例を調べる習慣のない人にとっては、要領をつかむまでは時間のかかる作業になります。
書籍がたくさんある
収益認識、リース会計といったIFRS特有の論点については、書籍がたくさん出版されています。書籍で調べる事ができ範囲は多いですよ。
外部コンテンツのメリットとデメリット
- 書籍を購入するメリット
- 書籍を購入するデメリット
書籍を購入するメリット
書籍を購入するメリットは2つあります。
- じっくり読む事が出来る
- 論点がまとまっており理解しやすい
書籍に関してはIFRS特有ではなく、様々な論点を理解する際に利用します。自分のペースで学習ができて、マーカーや付箋をして論点整理がしやすいので利用しました。
わたしがIFRS開示の時に参考にした2つの書籍を紹介します。
あずさ監査法人編集の書籍で、上場企業の経理を経験した人は内容が理解できると思います。それぞれの論点が詳しく記載されていて、理解するには十分な内容でした。
IFRSの原文を日本語訳した書籍です。注記を作成する場合は必須の書籍です。
IFRS関連で疑問が出た時は、ネットの情報ではなく書籍を読むを事をおススメします。ネットの情報は取引ごとの具体例が少なかったので。
書籍を購入するデメリット
書籍を購入するデメリットは1つあります。
- 相談が出来ない
デメリットは研究部と同じで、相談が出来ない事です。
日本基準の論点を調べる場合は、事例がたくさんあるので自分で答えを出す事が出来ますが、IFRSの場合は事例が少ないので自分で答えを出す事が出来ません。
やはり答えを出すには、監査法人の相談が必要になりますね。
学習方法のまとめ
IFRS開示プロジェクトに関わり、未経験ながらもIFRSの論点をまとめてきました。論点整理をして結論を出す方法をお伝えします。
IFRSの論点整理をする方法
- やれることは全部やる
- 監査法人の言われたことだけを信用しない
- 自分の出した答えを信用しない
論点整理は監査法人に聞いて、研究部を利用して、書籍を読んで答えを出すことで間違いを防げます。最初に楽をすると後で間違いが見つかって余計に時間がかかりますよ。
なので、監査法人に指摘をされても、自分で調べて納得することが重要です
IFRSのプロジェクトを完成は大変でした。途中は何度も間違ってやり直しの繰り返しでした。しかし、わたしはIFRS開示のメンバーとして開示ができて経験と自信がつきました。
『辛かったけど経験できてよかった』と感じていますよ!
未経験の人も多いので経験は不要です
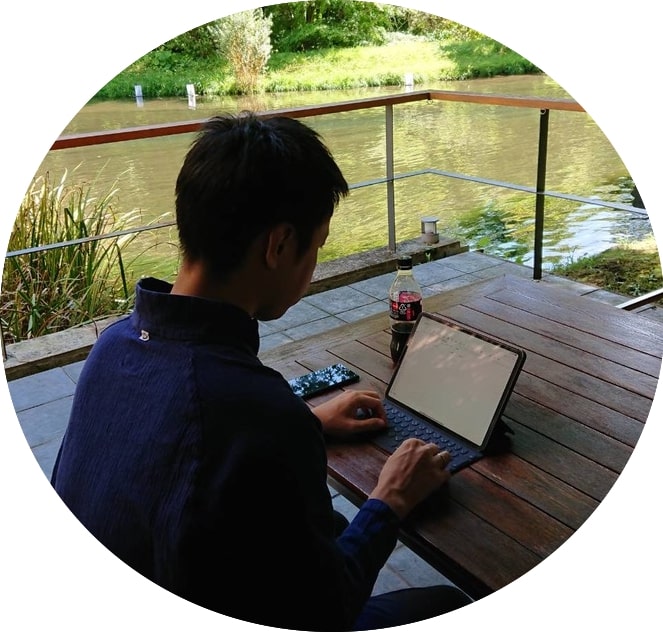
最初は誰でも未経験です。
私がプロジェクトに参加をした時は、IFRSの知識だけでなく連結に関する知識も不足していました。
毎日「他の人についていけるかな」「論点を正しく理解できているかな」そんな不安な毎日を送っていました
それでも前向きにプロジェクトに参加していたので、少しずつ知識を定着することができました。
未経験の業務をすることはとても不安なことですが、みんな同じ不安をかかえていますよ。
難しいことに挑戦をしているので、誰もがうまく理解できず悩んでいます。一人で悩むのはやめましょう!
IFRSの適用企業は増加している
IFRS適用会社は年々増加しています。新規上場をIFRS基準としている企業もあります。当初は2015年〜2016年に強制適用と言われていました。
しかし、東日本大震災による経済・産業界への影響が大きく、この時期での強制適用は見送られました。強制適用についての動きは止まっている状況です。
2021年9月のIFRS適用済・適用決定会社数
IFRS適用会社数:233社
IFRS適用決定会社数:7社
今後も増えていくと予想されるので、早い時期に経験すると今後の転職の幅が広がりますよ。
※『IFRSの動向を詳しく知りたい!』という人は、以下記事で詳しく解説しているので読んで下さいね。
-

-
【IFRSとは?】IFRS導入企業で働くベテラン経理が基礎を解説【国際会計基準とは?】
続きを見る
IFRS適用企業で働く方法
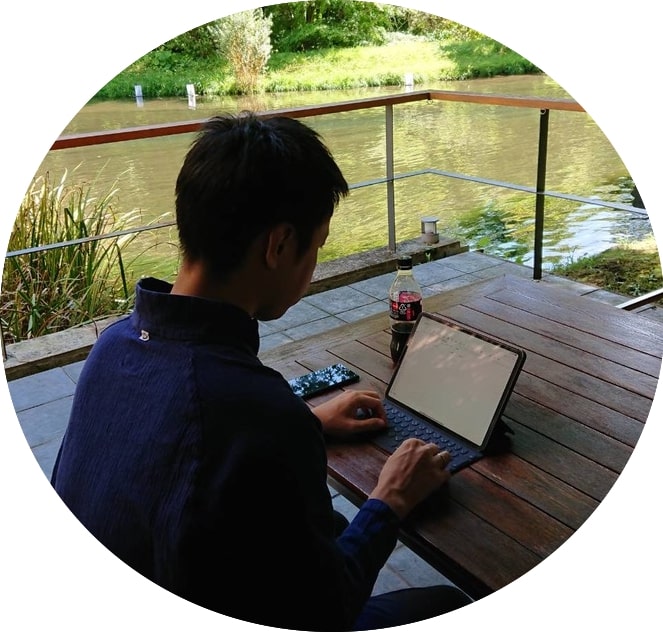
どちらの企業も『上場準備会社』か『上場会社』です。なので比較的大きい企業が対象となります。
※ 0円で転職の近道
IFRS適用企業で働くには業界最大級の非公開求人を誇るリクルートエージェントの登録がおすすめです。非公開公開にせざるを得ない魅力的な求人が多いですよ!
>> 【公式】リクルートエージェントの登録はこちら
「IFRS関連企業で働けるか?」のまとめ
ここまで読んだ方は、もしかすると「興味はあるけど、また勉強するのがわずわらしい」と思っているかもしれません。
しかし、今後のIFRSの状況は適用する企業が増えています。
今後も経理に関する仕事がしたい方は必須になるので思い切ってチャレンジをしてみましょう!私も苦労しましたが、経理を続けたあなたは真面目な人です
繰り返しですが未経験でも問題ありません。私は経理キャリアを積むためにIFRS関連企業で働くことをお勧めします。
※『IFRS学習方法を詳しく知りたい!』という人は、以下記事で詳しく解説しているので読んで下さいね。
-

-
【IFRS検定試験】IFRS適用の開示を成功させたベテラン経理が、資格の勉強方法を解説【アビタス】
続きを見る